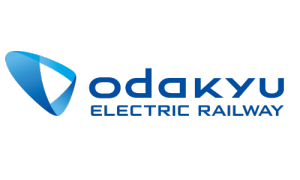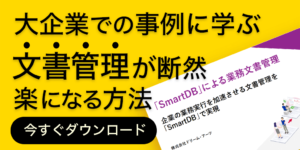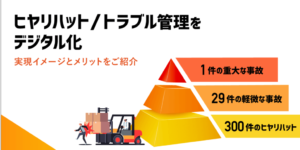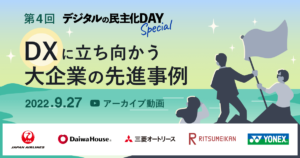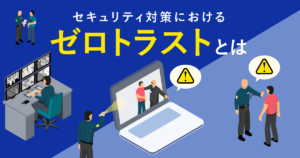事業の成長や拡大に伴い、多角化や複数拠点展開により、契約書の管理や契約関連業務はますます複雑化します。特に、契約プロセスに複数の部署や担当者が関わることで、「過去の契約書の検索に時間がかかる、承認の流れが見えづらい、契約期限を見落とす」などの課題が多くの企業で生じています。
これらの問題は情報分散や業務属人化などが原因です。解決をしないまま放っておくと、コンプライアンス違反などの経営リスクに直結します。
こうした課題を解決するのがCLM(Contract Lifecycle Management)です。CLMは、契約ライフサイクルマネジメントと呼ばれており、契約の企画・立案から終了まで、契約に関わる全プロセスを体系的に管理する手法を指します。
近年では、CLMをより効果的に運用するために、契約書作成から契約終了・更新までのプロセスを一気通貫で管理できる「CLMツール」が注目を集めています。
本記事では、CLMの基本概念からCLMツール導入によるメリット、選定ポイント、成功事例まで、契約管理業務の効率化に必要な情報を体系的に解説します。CLMツールの導入を検討されている方や、契約業務の課題解決を目指す方にとって、実践的な指針となる内容です。
目次 [閉じる]
CLM(契約ライフサイクル管理)とは
CLM(契約ライフサイクル管理)とは、「Contract Lifecycle Management」の頭文字をとった略称です。契約書の作成から審査、承認、締結、保管、更新、終了にいたるまで、契約に関する全プロセスを体系的に管理・最適化するアプローチを意味します。
具体的には、契約書の作成、法務・関係部署による審査、社内承認、相手方との締結、契約条件の履行管理、期限管理、更新判断、そして契約終了という一連の流れを、一元的に管理・最適化することを指します。
CLMは、この分断されたプロセスをひとつの流れとして捉え直し、契約業務全体の効率化とリスク管理の強化を目指すものです。
CLMツールとは
CLMの考え方を、実際の業務で実現するために開発されたのがCLMツールです。CLMシステムとも呼ばれています。CLMツールは、契約ライフサイクル全体をデジタル化し、各プロセスを自動化・可視化します。
電子契約の普及に伴い、テンプレート管理、承認ワークフローの自動化、アラート機能、契約データ分析など多様な機能を備えており、契約業務を効率的に処理できるようになります。
現在、多くの企業がCLMツールを導入することで、契約業務の標準化、ガバナンス強化、業務効率の大幅な改善を実現しています。
CLMツールと混同されやすい用語との違い
CLMツールを理解する上で、類似するシステムとの違いを明確にすることが重要です。特に混同されやすい「契約書管理システム」と「リーガルテックサービス」との違いについて解説します。
契約書管理システムとCLMツールの違い
契約書管理システムは、締結済みの契約書を保管・検索・管理することに特化したシステムです。主な役割は、過去の契約書をデータベース化し、必要なときにすぐ探し出せるようにすることです。基本的な文書管理機能に限定され、単体運用を基本とした設計になっています。
一方、CLMツールは、保管・管理だけでなく、契約ライフサイクル全体をカバーする包括的なシステムです。契約書の作成支援から審査、承認ワークフロー、締結プロセス、履行管理、更新判断、終了にまで、契約に関わる全業務を統合的に管理する点が大きな違いです。
また、CLMツールには契約書作成支援に特化するなど、特定フェーズに強みを持ちながらも契約ライフサイクル全体をカバーするシステムも存在します。業務システム連携を想定した設計となっており、より包括的な契約管理が可能です。
リーガルテックサービスとCLMツールの違い
リーガルテックは、「法律(Legal)」と「技術(Technology)」を組み合わせた概念で、IT技術で法務業務全般を効率化するサービスの総称です。さらに法務業務の効率化を目的としたITサービス全般のことをリーガルテックサービスといいます。
AIによる契約書レビュー支援、判例検索サービス、法務相談チャットボット、コンプライアンス審査支援など、その範囲は多岐にわたります。
企業の法務部門が利用することが多く、法務関連業務の幅広い領域をカバーしているのが特徴です。
CLMツールは、このリーガルテックという大きな枠組みのなかに含まれる、「契約管理に特化した専門ツール」と位置づけられます。リーガルテックサービスの一分野として、契約ライフサイクル管理に焦点を絞った機能を提供します。
近年、デジタル化の進展により契約書の量や種類が増えてきています。さらに法規制の強化に伴い、契約内容を正確に把握することや期限を管理することの重要性も高まっています。
こうした状況で、効率的かつリスクを抑えた契約業務の運用が企業には求められています。CLMツールの導入は、今後ビジネスの競争力を高めていくためにも、ますます重要視されることが予想されます。
CLMツールの種類

CLMツールは契約管理を包括的にサポートするツールですが、一口にCLMツールと言っても、その機能範囲には差があります。大きく分けると、契約業務全体を一元管理できる「統合型」と、特定のプロセスに特化した「特化型」の2タイプがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や解決したい課題に合ったものを選ぶことが重要です。
あわせて導入前には、機能範囲や連携の可否などを十分に把握しておきましょう。導入の目的や自社の業務フローに応じた適切な選定が、成功の鍵となります。
契約業務全体を一元管理できる「統合型」
契約書の作成からレビュー、締結、そして締結後の管理、更新まで、契約ライフサイクル全体をひとつのシステムで完結できるタイプです。以下のような包括的な機能により、契約業務全体の最適化を実現できます。
- 契約書テンプレート作成・管理
- 電子契約締結
- 承認ワークフロー
- 契約書保管・検索
- 期限管理・自動通知
- 契約データ分析・レポート
契約業務に関わる情報やプロセスをひとつのシステムにまとめることで、部門を横断した情報共有を促進します。
たとえば、営業担当者が契約書を起案し、法務部が内容を確認・承認、電子契約で締結し、その後の管理まで一貫してシステム上で実行可能です。すべてのプロセスが履歴として記録されるため、透明性の確保と内部統制の強化も実現できます。
このように、業務プロセスの標準化や内部統制の強化が図りやすくなり、効率化の実現に大きく貢献することが期待されます。
特定のプロセスに特化した「特化型」
電子契約や承認ワークフロー、契約書の管理など、契約ライフサイクルの一部分に特化した機能を提供するタイプです。
たとえば「押印業務の手間を削減したい」「複雑な承認フローを効率的にシステム化したい」といった、具体的な課題に的確に対応できる点が大きなメリットです。また、機能を絞ることで操作がシンプルになり、現場への導入や習得がスムーズに進むのも特徴です。
CLMツールの特化型は、契約業務全体を見据えつつも、特定のフェーズにフォーカスして効率化を図ることができる点が大きな強みです。また、必要に応じてほかのシステムと連携することで、より広範囲な契約管理にも対応可能です。将来的な管理範囲の拡大を考慮し、拡張性や連携のしやすさを事前に確認しておくことが重要です。組織の成長や契約件数の増加に合わせて、段階的に包括的なシステムへの移行も検討しましょう。
CLMツールで実現できる5つのこと
CLMツールは、契約ライフサイクル全体のデジタル化を通じて契約業務のプロセスを標準化し、企業のコンプライアンス体制強化と業務効率化に貢献します。具体的にどのようなことが実現できるのか、5つのポイントで見ていきましょう。
1.契約情報の一元管理
CLMツールの中核機能は、契約に関するあらゆる情報をひとつのシステムに集約することです。契約書ファイルはもちろん、契約相手先情報、契約期限、責任者、リスク評価、承認履歴など、契約に関わるすべてのデータを統合管理できます。
これにより属人化を防ぎ、組織として情報資産を適切に管理できます。組織改編時の業務引き継ぎや、グループ会社間での契約情報共有もスムーズになり、企業規模の拡大にも対応可能です。
2.アラート機能による確認漏れの防止
契約期限の更新漏れや確認漏れは、ビジネスにおいて大きな損失につながりかねません。CLMツールは、これらのリスクを自動アラート機能で防止します。
具体的には、契約更新期限の事前通知、承認待ち案件の自動リマインド、契約条件変更の通知など、重要なタイミングで関係者に自動的に通知を送信します。これにより、従来の手動管理や個別対応に頼っていた管理方法から脱却し、更新漏れや意図しない自動更新のリスクを未然に防げます。
3.契約データ分析による戦略的意思決定の支援
CLMツールに蓄積された契約データは、戦略的な意思決定を支援する貴重な情報資産となります。契約件数、取引先分析、契約金額の推移、契約期間の傾向など、あらゆる角度から契約実績を分析できます。
「どの取引先が収益性の高い契約を多く保有しているか」「過去の契約条件が利益率にどう影響しているか」「どの契約タイプで支払い遅延や更新拒否が多いか」といった傾向をデータから可視化が可能です。これにより、価格交渉や契約条件の見直し、重点取引先の選定など、実務に直結した判断がしやすくなります。
4.履歴とログの共有による契約業務の透明化
CLMツールは、契約書の作成から締結まで「だれが、いつ、なにを判断したか」という全プロセスを時系列で記録します。承認者の判断、修正履歴、関係者間のやり取りなど、契約に関わるすべての情報がログとして保存されます。
この透明性により、監査対応や説明責任の履行が格段に容易になります。また、過去の交渉経緯や修正意図を参照できるため、類似案件の際に「なぜこの条項になったのか」といった背景を理解しやすく、「どの部門の判断でこの条件が確定したのか」「なぜこの価格で合意したのか」なども把握でき、一貫した判断を下すのに役立ちます。
5.契約ライフサイクル全体のリスクの可視化・最小化
CLMツールは、契約ライフサイクル全体のリスクを可視化し、予防的な管理によりリスクを最小化します。
契約期限の管理、自動更新条項の把握、リスク評価の標準化など、CLMツールが提供するのは包括的なリスク管理機能です。承認フローを標準化することで、然るべき部門のチェックが漏れるといった人的ミスを防ぎます。
これにより、契約違反や更新忘れ、自社にとって不適切な条項の見落としなどの重大なリスクを事前に防止し、企業全体のガバナンスを向上させることができます。
CLMツールを導入するメリット
CLMツールを導入することで得られる代表的な効果について、それぞれ詳しく解説します。
- 契約業務のスピードが向上する
- ミス・ヌケモレの防止につながる
- 業務の属人化を解消できる
- 契約業務のコストを削減できる
1.契約業務のスピードが向上する
CLMツールの導入により、契約業務の処理速度が大幅に向上します。ツール上で契約情報を一元管理することで、過去の契約内容やステータス、更新期限などを即座に検索・参照できるようになり、問い合わせ対応や内容確認にかかる時間が大幅に短縮されます。
さらに、テンプレートやワークフローの自動化と組み合わせることで、契約書作成から締結までのプロセス全体も効率化。承認者の不在による稟議の滞留や、紙の契約書の印刷・製本・郵送といった非効率な作業を減らすことができ、ビジネス機会を逃すリスクを抑えつつ、競争優位の確保にもつながります。
2.ミス・ヌケモレの防止につながる
CLMツールに搭載された契約条文のチェックリスト、入力補助機能、過去の履歴参照機能により、契約書作成における人的ミスを削減できます。
あらかじめ設定されたルールに基づき業務プロセスが自動で進行するため、承認漏れや誤ったテンプレートの使用といった人的ミスの発生を未然に防ぎます。条項の記載漏れ、記述ミス、不適切な条件設定など、従来発生しがちなエラーを予防します。
標準化されたテンプレートとレビュー機能により、担当者のスキルレベルに関わらず一定品質の契約書を作成できるため、全社の契約業務を標準化し、統制の取れた状態を維持できます。これにより、内部統制やコンプライアンスの強化につながります。
3.業務の属人化を解消できる
契約書の作成から審査、承認、管理までの流れをCLMツールに集約することで、特定の担当者に依存する業務体制から脱却できます。ツール内に蓄積されたテンプレート、進捗管理機能、作業履歴により、業務の引き継ぎも格段にスムーズになるでしょう。
担当者の異動や休職・退職時も、契約業務への影響を最小限に抑えられるため、業務継続性への影響を最小限に抑えられます。
4.契約業務のコストを削減できる
契約書の印刷や発送、物理的な保管にかかる費用は、年間を通じて見ると少なくありません。CLMツールを導入すれば、電子化によって紙ベースの業務を削減し、コストを抑えることが可能です。
さらに、業務の進捗をリアルタイムで把握できるようになるため、確認作業やリマインド業務の手間も減り、人的リソースの最適化にもつながります。契約業務にかかっていた人件費(間接コスト)も大幅に圧縮できるため、企業全体のコストも削減することができるでしょう。
契約業務におけるCLMツールの活用ポイント
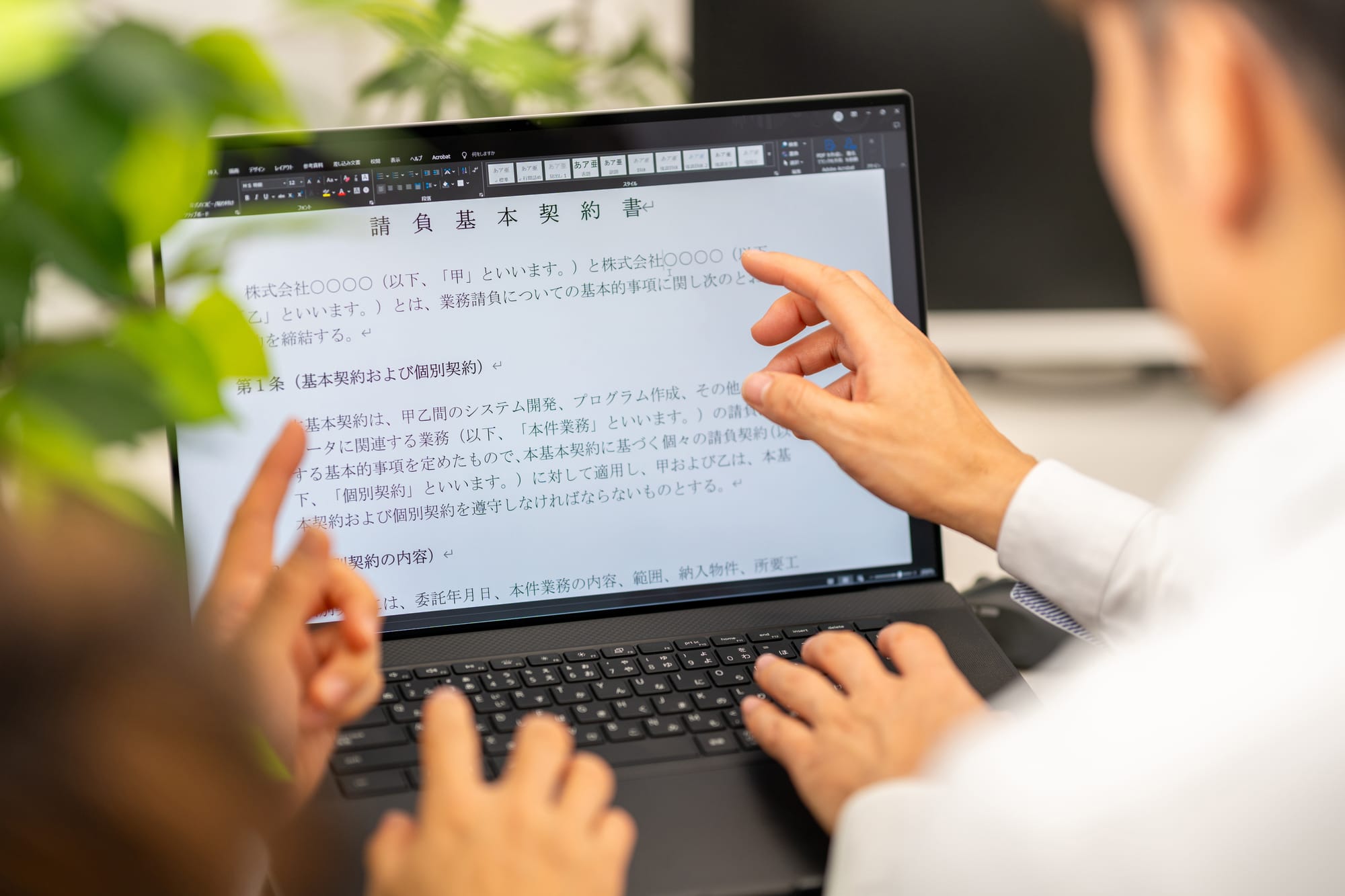
CLMツールはで具体的にどのようなことが実現できるのか、業務プロセス別に説明します。
契約書の作成
契約書の作成では、定型文書テンプレートや自動入力機能、過去の履歴を参照する機能などが便利です。定型的な契約書であれば、CLMツールの指示にしたがって入力を進めることで、専門的な法務知識がなくても、高品質な契約書を迅速に作成できます。
頻繁に使用する条項をテンプレート化することで、文言の整合性確認作業も不要になります。これにより、担当者によるばらつきや記載ミスを防止し、契約書の品質を一定に保つことができます。
契約書の審査
CLMツールを活用すると、契約書の審査では、法務部や経理部など各部門でのレビュー(確認・承認)をワークフローとして構築できるようになります。承認ステータスをリアルタイムで把握できるため、属人化や進行の遅延を防げる点も特徴です。
また、各段階でのコメントや修正履歴も記録されるため、証跡管理や監査対応にも有効です。確認・承認の流れをCLMツールで標準化することで、ミスのリスクを抑えた審査体制を構築できます。
社内稟議・締結
社内稟議・締結のプロセスでは、稟議書のデジタル化と電子契約の活用により、従来のボトルネックを解消できます。上長の承認や締結作業がスムーズに進むようになるため、承認プロセスの属人化や物理的距離などで生じるタイムロスを削減します。
契約書の管理や更新
契約書の管理においては、CLMツールで各契約の有効期限や更新のタイミングを自動で通知することが可能です。契約期間の管理を徹底することで、更新忘れや失効のリスクを防止できます。
煩雑な個別管理から脱却し、企業としての契約管理の精度と信頼性を高められる点がメリットです。契約書の管理においては、CLMツールの自動通知・アラート機能と一元管理機能により、契約期限の見逃しや更新忘れを防止できます。
加えて、更新判断支援や契約条件変更の履歴管理、契約パフォーマンス分析などの機能により、契約管理の精度と信頼性を大幅に向上させ、コンプライアンスリスクを最小化できます。契約データの分析により、更新判断や条件見直しの根拠となる情報を得ることも可能です。
これにより個別の手動管理から脱却し、組織的な契約管理を実現できます。
CLMツールを選ぶときの比較ポイント
CLMツールは、契約業務全体のプロセスを改革する重要なIT投資です。適切なCLMツールを導入することで、契約業務の効率化だけでなく、コンプライアンス強化やリスク管理の向上も実現できます。自社に最適なツールを選ぶために、必ず確認すべき5つのポイントを解説します。
1.自社に必要な機能を満たしているか
CLMツール選定においてもっとも重要なのは、自社の契約業務に必要な機能が適切に実装されているかどうかです。
まずは、「契約書の検索に時間がかかる」「承認フローが複雑だ」といった現場の課題を洗い出しましょう。特に契約件数が多い企業や承認ワークフローが複雑な組織では、日常業務で頻繁に使用する機能の使いやすさが生産性につながります。
以下の3つの核となる機能について、自社の業務実態と照らし合わせて評価していきましょう。
検索性の高さ
日常的な契約業務において、必要な契約書を迅速に特定できる検索性の高さは業務効率を大きく左右します。「過去3年以内にA社と締結した契約書をすべて検索」「自動更新が設定されている契約のみ抽出」などの条件検索ができると、実務で非常に役立ちます。
契約書の内容、契約先の企業名、契約期間、金額範囲、契約ステータスなど、複数の条件を組み合わせた詳細検索が可能かどうかも確認しましょう。
契約書の可視化と一元管理
契約業務の属人化を解消し、業務継続性を確保するためには、各契約が「だれのボールで」「どんなステータスか」が一目でわかる仕組みが欠かせません。
個々の契約書のステータス(作成中、法務審査中、稟議承認待ち、締結済みなど)を一覧でリアルタイムに把握できると、チームメンバーは契約の進捗状況を確認でき、どの契約にどの程度の優先度で対応すべきかを適切に判断できるようになります。
契約データベースの有無
契約情報を単なるファイルではなく、分析可能なデータとして構造化して管理できるかが重要です。契約先・契約日・更新日・自動更新の有無・担当者などのメタデータを構造化して管理することで、「来四半期に更新期限を迎える契約の総額」や「特定取引先との契約条件の変遷」といった戦略的な分析が可能になります。
2.契約ライフサイクルをどこまでカバーできるか
前述のとおり、CLMツールには契約書の作成から管理までを一貫しておこなえる統合型のツールもあれば、電子契約やワークフローなど特定領域に特化したツールもあります。
ツールによってカバーできる契約ライフサイクルの範囲は異なるため、「まずは承認プロセスからデジタル化したい」のか、「全社で契約業務全体を刷新したい」のか、自社の導入目的とステップに合わせて、最適な機能範囲のツールを選びましょう。
全社規模での一括導入を目指すのか、特定部門から開始して段階的に拡張するのかによって、最適な製品選択は変わってきます。
3.セキュリティ対策が整っているか
契約書は企業の重要情報・機密情報の宝庫です。契約書には取引条件、価格情報、知的財産に関する条項など、競合他社に知られることで競争上の不利益を被る可能性のある情報が含まれているため、堅牢なセキュリティ対策が施されているかは、ツール選定における必須要件です。
基本的なセキュリティ要件として、データの暗号化(保存時・転送時の両方)、アクセス権限の制御、監査ログの記録・保持機能、定期的なセキュリティ監査の実施などが挙げられます。また、障害時のデータ復旧体制やバックアップ方針についても事前に確認することが重要です。
第三者機関による客観的な評価として、ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)やSOC2 Type 2などの国際的なセキュリティ認証の取得状況を参考にすることを推奨します。これらの認証は、セキュリティ管理体制が継続的に維持・改善されていることを証明する重要な指標となります。
4. ほかシステムと柔軟に連携できるか
契約業務は法務部門単独で完結するものではなく、営業、購買、経理、人事など複数部門の既存業務プロセスと密接に関連しています。営業支援システム(CRM)や基幹システム(ERP)など、ほかの多くのシステムと関連するため、これらとの柔軟な連携が業務効率を大きく左右します。
実際、弊社が実施した大企業従業員500名を対象とする調査では、契約業務のデジタル化を推進している企業の最大の課題が「システム間の連携ができていない」ことによる業務の分断でした。
API連携の柔軟性や、以下のような主要システムとの連携実績などを事前に確認し、サイロ化を防ぐことが重要です。
- CRMプラットフォーム(Salesforce、HubSpot)
- ERPシステム(SAP、Oracle、Microsoft Dynamics)
- 電子契約サービス(DocuSign、Adobe Sign)
- 会計システム・請求管理システム
- プロジェクト管理ツール
連携機能の評価では、単に連携可能であることを確認するだけでなく、データの同期頻度、双方向連携の可否、連携時のデータ変換・マッピング機能、エラー処理・復旧機能などの実装詳細も検討しましょう。
大企業の従業員500名に聞いた「契約業務のデジタル化」に関する調査レポートダウンロード
5. 全社向けの設計かどうか
CLMツールを全社で活用するには、法務部門だけでなく、営業、購買、経理など多様な職種のユーザーが直感的に操作できるユーザーインターフェースと、情報の機密性レベルに応じた適切なアクセス制御機能が両立していることが重要です。
ユーザビリティの確認ポイント
専門知識を持たない非法務部門のユーザーでも、テンプレート選択と必要事項の入力だけで契約申請を完了できるような、直感的なUX(ユーザーエクスペリエンス)が提供されているかを確認しましょう。また、モバイル対応により外出先からの承認作業が可能であれば、契約プロセスの迅速化にも貢献します。
アクセス制御の詳細設定
契約の重要度に応じて「この部署には閲覧権限のみ」「この役職者には承認権限を付与する」といった、「閲覧権限」「編集権限」「承認権限」「削除権限」などの詳細な権限設定ができる機能が必要です。
適切な権限管理により、情報漏洩リスクを最小化しながら、必要な情報を適切な関係者と共有できる環境を構築できます。全社展開を見据え、使いやすさとセキュリティ統制を両立できるツールを選びましょう。
ノーコードツールで自社最適なCLMを構築した事例
ここまでCLMツールの選び方を解説してきましたが、市販の専用ツールを導入したものの、「機能が複雑で使いこなせない」「自社の特殊な業務フローに合わせられず、結局手作業が残ってしまった」という声も少なくありません。
このような「ツールと業務のミスマッチ」を解決するアプローチとして、いま注目されているのがノーコード開発プラットフォームの活用です。
ノーコードとは、プログラミングの知識がなくても、現場の担当者が主体となって、自社の業務に本当にフィットしたシステムを構築できる手法です。詳しくは「ノーコードとは?特徴やメリット・デメリット、ノーコードツールの選び方を紹介」をご覧ください。
弊社ではノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」を提供しています。Webデータベースとワークフロー機能を備えたノーコード開発基盤として、多くの企業の業務デジタル化を実現してきました。
ここでは専用CLMツールやCLMシステムから、ノーコード開発基盤「SmartDB」を導入して、契約管理業務プロセス全体のデジタル化に取り組むグリー株式会社、LINEヤフー株式会社の事例を紹介します。
資料ダウンロード申し込み|契約管理の‟あるある課題”、ノーコード開発で解決するためのポイントとは
グリー株式会社
同社では従来のシステムで契約業務の非効率や統制面での不十分さが課題となっていました。これらを解決するため、契約管理業務を一元管理できるシステムとして「SmartDB」を導入されました。
【従来のシステムの課題】
- 過去の契約データを再利用できず、契約書の作成に手間が発生
- 承認ステップが手動設定のため、本来対応すべき担当者からの確認が漏れている
- 依頼の発生状況・審査状況が確認しづらく、滞留の検知が困難
- 編集権限を制御できず、契約審査の完了後も改ざんのリスクがある
- 専用CLMツールでは業務プロセス全体をカバーしきれなかった
- システム連携ができず手作業が必要だった
【「SmartDB」導入で期待される効果】
- 過去データの再利用や業務連携で登録の手間を削減
- 承認ステップの自動設定で決裁規程の遵守を徹底
- 検索性の向上、権限管理でデータ活用促進と統制強化を両立
関連記事:グリー、グループ会社横断の契約管理業務にSmartDB®︎を導入
LINEヤフー株式会社
同社では複雑化・硬直化した自社開発システムが課題となっていましたが、柔軟な契約管理と外部システムとの連携を実現し、変化への迅速な対応をするために「SmartDB」を導入されています。
【従来のシステムの課題】
- これまで契約管理では、自社開発のスクラッチシステムを利用していた
- 経営環境の変化などによりシステムに柔軟な対応が求められるなかで、システム改修のたびに多大なコストや時間を要する状態だった
- 改修を続けて複雑化したシステムは、そもそも改修すること自体が難しいという課題があった
- 既存システムでは外部システムとの連携ができない課題も発生していた
【「SmartDB」導入で期待される効果】
- 変契約管理業務をはじめ自社の業務に応じた柔軟な文書管理を実現
- 社内外の環境変化を素早くシステムに反映
- ほかシステムとも柔軟なAPI連携が可能
関連記事:契約管理業務のデジタル化にSmartDB®をヤフーが導入
※現在は社名変更しLINEヤフー株式会社となっています。
これらの成功事例は、従来のCLMツールの限界を克服し、ノーコード開発プラットフォームの活用により、企業固有の要件に最適化されたCLMシステム構築が可能であることを実証しています。
契約管理プロセスを一気通貫で実現するなら「SmartDB」
本記事では、CLM(契約ライフサイクルマネジメント)の基本から、CLMツール導入のメリット、選定ポイントまでを解説しました。
契約業務の効率化やガバナンス強化を実現するには、契約ライフサイクル全体を見渡し、プロセス全体を適切に管理する視点が欠かせません。
CLMツールは、契約書の作成から締結・管理までをカバーする強力な手段ですが、製品によっては「自社の業務フローに合いにくい」「細かな改修が難しい」といった課題が生じることもあります。
とくに、複雑で柔軟性を求められる業務プロセスには、一般的なCLMツールでは対応が難しいケースもあるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、ノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」です。
「SmartDB」は、Webデータベース機能とワークフロー機能を兼ね備えており、プログラミング知識がなくても、自社の業務に合わせた契約管理システムを構築できます。また、大企業にも選ばれる堅牢なセキュリティを標準で提供しているため、機密性の高い契約業務にも安心して活用できます。
関連:大企業のDX実現に欠かせない「SmartDB」の安全対策
一般的なCLMツールではカバーしきれない契約前の取引先与信判断や法務相談、ドラフト作成、複雑な承認稟議といったプロセスまで、一気通貫でデジタル化できるのが最大の強みです。契約前の交渉や稟議申請、部門間調整といった周辺業務も一貫して管理します。
実際に、SmartDB®︎で構築した稟議業務アプリが2,000名規模で利用されている事例もあります。
関連記事:東急の本社約2,000 名が利用する稟議・法務相談業務にSmartDB®︎を導入
「SmartDB」は、データと業務プロセスの両方を保持しているため、AIを業務プロセスに“自然に溶け込ませる”ことが可能です。今後は、大企業の実務に即した形で活用できる、「SmartDB」のAI機能群を順次リリースしていく予定です。
関連:⼤企業におけるAI活⽤の新たな独⾃コンセプト「DAPA」とは?
現場が主体となることで継続的に業務改善を進めながら、業務に応じて柔軟にシステムを改修することも可能です。
自社の運用に本当にフィットする契約管理の仕組みを構築したい、とお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

3分でわかる「SmartDB」
大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。
詳細・お申し込みはこちら